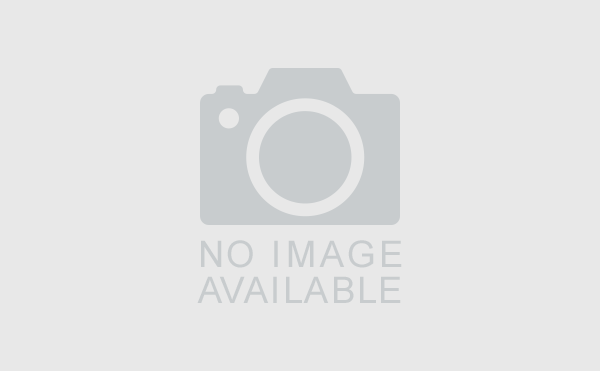「察してほしい」をやめてみたら
最近、グループカウンセリングで「聴く」「伝える」をテーマにした回を続けて行いました。
そこであらためて感じたのは、多くの人が心のどこかで「分かってほしい」「察してほしい」と願いながら、本当の気持ちを言葉にできずにいるということです。
してほしいことがあるのに言えない。嫌だと思っているのに伝えられない。
相手を思って黙っているつもりが、期待は募り、やがて諦めや不満に変わっていく。そんな場面に何度も出会いました。
でも、その一方で——ほんの少し勇気を出して言葉にしただけで、状況が大きく動き出す人たちもいました。
「察してほしい」という気持ちは、決してわがままでも未熟でもありません。
それは、自分の中にある大切な想いを守ろうとする自然な反応でもあるからです。
傷つきたくない。否定されたくない。迷惑をかけたくない。嫌われたくない。
そんな静かな恐れがあると、人は「伝える」という行為の前で立ち止まります。
本当は「もっとこうしてほしい」「私はこう感じている」と言いたいのに、それによって関係が壊れてしまうのではないかと不安になる。
だから、人は願ってしまうのです——「言わなくても気づいてほしい」「察してほしい」と。
けれど、その想いが強くなるほど、私たちは自分の気持ちを内側に押し込め、相手の反応を待つばかりになってしまいます。
一方で、「察してほしい」と同じくらい多くの人が、「察してあげなきゃ」と自分を追い込んでいます。
相手の気持ちを汲み取れなかったら冷たい人のように思われるのでは、と不安になったり。相手を思うあまり、言葉よりも想像に頼ってしまったり。
でも、人の気持ちは想像以上に複雑で、当たっていることもあれば、見当違いのこともある。
「分かるよ」と言い切ることが、時に相手の痛みを軽く扱ってしまうこともあります。
心理士である私はよく「心理士だから人の気持ちは何でも分かってしまうんでしょ?」と言われますが、残念ながら全く分かりません(笑)
だからこそ、私は思うのです。
分からないからこそ、理解しようとし続けること。
分かってもらいたいからこそ、伝え続けること。
そして、その往復をやめないことが、人と関わる上で最も大切なのではないかと。
人と人は違うからこそ、それを前提として丁寧に聴き、丁寧に伝える。
そこから関係は少しずつ育っていくのだと思います。
「察してほしい」は相手への信頼の表れでもあるし、「察しなきゃ」は人を思うやさしさの表れでもあります。
けれど、そこにとどまると、関係の主導権を相手に渡してしまう。
相手がどう感じ、どう動くかは、自分にはコントロールできないもの。
だからこそ、「察してもらえない」と落ち込むよりも、「どうすれば伝わるか」を考える方が、自分の人生を自分で動かすことにつながります。
伝えることは、我慢をやめること。
理解しようとすることは、押しつけを手放すこと。
どちらも、関係をあたたかくするための誠実な行為だと思うのです。
たとえばこんな小さなことからでも。
「いま忙しい?少し相談してもいい?」と、声をかける。
「こうしてもらえると助かる」と、具体的に伝えてみる。
「私にはこう見えたけれど、あなたはどう思う?」と、相手に確かめる。
それだけで、誤解が減り、関係がやわらかく動き出すことがあります。
人は、完全に分かり合うことはできません。
でも、分かろうとする努力と、分かってもらうための言葉を紡ぐことはできる。
その積み重ねが、互いの違いを越えて、信頼を育てていくのだと思います。
「察してほしい」も「察しなきゃ」も、少しだけ手放して、
今日も誰かと、丁寧に聴き、丁寧に伝えていけたらいいですね。
そこであらためて感じたのは、多くの人が心のどこかで「分かってほしい」「察してほしい」と願いながら、本当の気持ちを言葉にできずにいるということです。
してほしいことがあるのに言えない。嫌だと思っているのに伝えられない。
相手を思って黙っているつもりが、期待は募り、やがて諦めや不満に変わっていく。そんな場面に何度も出会いました。
でも、その一方で——ほんの少し勇気を出して言葉にしただけで、状況が大きく動き出す人たちもいました。
「察してほしい」という気持ちは、決してわがままでも未熟でもありません。
それは、自分の中にある大切な想いを守ろうとする自然な反応でもあるからです。
傷つきたくない。否定されたくない。迷惑をかけたくない。嫌われたくない。
そんな静かな恐れがあると、人は「伝える」という行為の前で立ち止まります。
本当は「もっとこうしてほしい」「私はこう感じている」と言いたいのに、それによって関係が壊れてしまうのではないかと不安になる。
だから、人は願ってしまうのです——「言わなくても気づいてほしい」「察してほしい」と。
けれど、その想いが強くなるほど、私たちは自分の気持ちを内側に押し込め、相手の反応を待つばかりになってしまいます。
一方で、「察してほしい」と同じくらい多くの人が、「察してあげなきゃ」と自分を追い込んでいます。
相手の気持ちを汲み取れなかったら冷たい人のように思われるのでは、と不安になったり。相手を思うあまり、言葉よりも想像に頼ってしまったり。
でも、人の気持ちは想像以上に複雑で、当たっていることもあれば、見当違いのこともある。
「分かるよ」と言い切ることが、時に相手の痛みを軽く扱ってしまうこともあります。
心理士である私はよく「心理士だから人の気持ちは何でも分かってしまうんでしょ?」と言われますが、残念ながら全く分かりません(笑)
だからこそ、私は思うのです。
分からないからこそ、理解しようとし続けること。
分かってもらいたいからこそ、伝え続けること。
そして、その往復をやめないことが、人と関わる上で最も大切なのではないかと。
人と人は違うからこそ、それを前提として丁寧に聴き、丁寧に伝える。
そこから関係は少しずつ育っていくのだと思います。
「察してほしい」は相手への信頼の表れでもあるし、「察しなきゃ」は人を思うやさしさの表れでもあります。
けれど、そこにとどまると、関係の主導権を相手に渡してしまう。
相手がどう感じ、どう動くかは、自分にはコントロールできないもの。
だからこそ、「察してもらえない」と落ち込むよりも、「どうすれば伝わるか」を考える方が、自分の人生を自分で動かすことにつながります。
伝えることは、我慢をやめること。
理解しようとすることは、押しつけを手放すこと。
どちらも、関係をあたたかくするための誠実な行為だと思うのです。
たとえばこんな小さなことからでも。
「いま忙しい?少し相談してもいい?」と、声をかける。
「こうしてもらえると助かる」と、具体的に伝えてみる。
「私にはこう見えたけれど、あなたはどう思う?」と、相手に確かめる。
それだけで、誤解が減り、関係がやわらかく動き出すことがあります。
人は、完全に分かり合うことはできません。
でも、分かろうとする努力と、分かってもらうための言葉を紡ぐことはできる。
その積み重ねが、互いの違いを越えて、信頼を育てていくのだと思います。
「察してほしい」も「察しなきゃ」も、少しだけ手放して、
今日も誰かと、丁寧に聴き、丁寧に伝えていけたらいいですね。